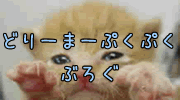混沌の時代だからこそ「答えは自分たちの中にある」という確信を
はじめに
「混沌こそが運動のエネルギーをつくり出す」―こう語る河野さんは、障がい者問題総合誌「そよ風のように街に出よう」編集長を務めるほか、著作も多数で、豊能障害者労働センターを創設し、代表を長年勤めるなど、関西の障がい者運動を創りあげてきた1人です。
河野さんが社会運動に目覚めた原点は、キューバ革命だそうです。中学卒業後、酒屋の店員として働いていた河野さんは、安保闘争の盛り上がりに触発され、浅沼社会党委員長の暗殺に危機感を抱く、時代に敏感な青年でした。「俺も何かやらなければ」という思いを胸に、社会党の青年組織である社会主義青年同盟のメンバーとなり、書記として活動を開始します。
以後、半世紀にわたる河野さんの歩みは、紆余曲折はありながらも、障がい者の権利実現・生きるための闘いに収斂されていきました。左翼として出発した河野さんが、マルクス主義の限界を感じ、「愛と正義を否定する」という辛辣な行動綱領を掲げて登場してきた青い芝の会(脳性マヒ者当事者組織)の運動に影響を受けながら、平等とは何なのか? 働くこととは何なのか?を考え続けてきた半生をお聞きしました。連載で紹介します(文責・編集部)
手探りの中で「さよならCP」上映会
障がい者との関わりはOさんとの出会いで始まりました。小児マヒの後遺症を抱えながら建具職人として働いていたOさんは、友人であると同時に運動仲間でもありました。1971年、彼と東京・日比谷公園での狭山闘争に参加した時です。集会場でヘルメットを被り車イスに乗った障がい者を見ます。
なぜ、障がい者が部落解放運動に参加するのか?聞いたら、「介護の学生が『映画を見に行こう』というので外出したらここへ来た」との答でした。本人の意向を無視し、いわば欺して連れてこられていたのです。「人権」を主張する社会運動の中でさえ、障がい者の主体性は無視されていたのです。
70年安保・沖縄奪還・部落解放闘争など様々な社会運動に関わっていましたが、どうもしっくり来ない感覚があり、この事件をきっかけにしてOさんと一緒に大阪で「障がい者解放の会」を立ち上げ、手探りの中で運動を始めました。
しかし身の回りに障がい者はほとんど居なかったし、どんな生活をしているのか全く知らないという現実から出発しなければなりませんでした。当時、障がい者は、施設か家庭に閉じ込められていたからです。
当時大学で起こり始めた「障がい者の聴講を勝ち取る会」に参加もしましたが、私たちは、まず障がい者に外に出て集まってもらう場を作ろうと、「さよならCP」の上映会を企画しました。この映画は、CP(脳性マヒ)当事者組織である「青い芝の会」の人々の生活と思想をカメラに収めた、原一男監督のドキュメンタリー映画です。
この映画を通して障がい者解放運動の創設者・旗手であった横塚晃一氏を知ります。彼は「愛によって造られた施設」や「殺すことが愛であるとする親」への批判を行い、「泣きながらでも親不孝を詫びながらでも、親の偏愛をけっ飛ばさねばならないのが我々の宿命である」という有名な一文を提示した人物です。
上映会には毎回多数の参加者があり、成功を収めますが、そこからが大変でした。介護者がいないのです。当時、ヘルパー制度なんて影も形もない頃です。5人の健常者に対して数十人の要介護者という状態で、バタバタ忙しく動き回りながら、優生保護法反対運動(74年)、養護学校義務化阻止闘争(79年)などに取り組んでいきました。この頃、若き楠敏雄さん(前号参照)と出会っています。
養護学校義務化阻止闘争は、学校教育から完全に排除されてきた脳性マヒの障がい者が、もう一度教育を奪い返したいという願いが込められた運動であり、自分たちの子どもの世代が養護学校という別学体制のもとで育っていくことへの強い怒りがありました。弱い者の教育と強い者のための教育が並立し、制度として固定化されてしまうことは教育全体をダメにしてしまいます。
「みんな同じ労働者」という虚構が崩れて
それまで私は、社会の仕組みや人間解放は、階級理論で全て説明できると信じていました。しかし、横塚晃一さんは、「労働者の中にある能力主義を克服しないかぎり、資本家階級には勝てないし、人間解放にも到達し得ない」と明確に語ります。世界の労働運動は労働者の中にある能力主義に目を向けず、お題目として団結を叫ぶだけだったために負け続けてきたと指摘されました。目から鱗が取れた思いでした。「みんな同じ労働者」という虚構が崩れました。労働者階級といっても能力も生活環境も夢もみんな違うという当たり前の事実に気づかされました。
自分が信じてきたマルクス主義は、結局、能力のある健常者の論理でしかないということを教えてもらいました。この挫折が障がい者運動に本腰を入れるきっかけとなりました。
混沌とし非合理な情熱こそ重要
依って立つ理論も過去の経験・実践もない中で運動を始めましたが、障がい者差別は至るところにありました。街はバリアだらけで、バスの乗車拒否も日常茶飯事でした。
阪神野田駅で視覚障がい者がホームから転落し、足を切断した事故の糾弾闘争、郵便投票制度への批判など、毎日出かけてビラを撒き、糾弾闘争を行い、小さな古い文化住宅に帰ってきては、酒を酌み交わしながら大激論という日々でした。手当たり次第に社会を批判し告発するという無秩序な運動でした。
今から思うと、ゴールは見えず、手当たり次第に社会に怒りをぶちまけるという混沌としたあの時代こそが、現在に繋がる障がい者運動と社会福祉制度の基礎を作ったのだと思います。
混沌とした時代のすばらしさの1つが、「答えは全て自分たちの中にある」という確信です。これは今の若い障がい者にも是非持って欲しい確信です。
国際権利条約や「合理的配慮義務」といった外部からの理論や法的枠組みを利用することは必要ですが、内側から湧き出る怒こそが社会を変える力です。
70年代、80年代の混沌とした運動が今見直されています。しかしそれは、運動の「理論化」ではなく、あの時代の非合理な感情や情熱こそが、今一度見直されるべきでしょう。
現在の社会運動は、障がい者運動に限らずデータを駆使し、数値化された合理的な答えを求めるという傾向になっています。私はこれには反対です。なぜなら、合理的な一線を引く「制度」というものは、必ずそこからはじき飛ばされる人間を生み出すからです。誰かを排除するのではなく、非合理的といわれようが、人間の生を丸ごと理解し、肯定しようとするのが障がい者運動の神髄だと思っています。
人間が生きる上でなくてはならない「愛」や「感動」や「涙」は、数値化できない非合理なものです。数値化できない非合理なものを含み込んでこそ障がい者運動は、輝きを取り戻すことができると信じています。(次号に続く)
(2009/05/15)