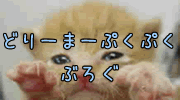特集:「生きてるだけでバンザイ」河野秀忠
「愛」と「感動」生む闘いを!
「答えは自分たちの中にあるという確信を持て」と語る河野秀忠さんのインタビュー後半です。左翼として出発した河野さんは、70年安保の敗北後、障がい者のOさんと出会い、共同でドキュメンタリー映画「さよならCP」の上映運動から障がい者市民運動を始め、養護学校義務化阻止闘争などに取り組んでいきました。
そうしたなか、マルクス主義が結局、能力のある健常者の論理でしかないのではないかという疑問が生じ、青い芝の会(脳性マヒ者当事者組織)の運動に影響を受けながら、もう一度、平等とは何なのか? 働くことの意味を考え続けてきました。(文責・編集部)
社会の目的は「命を守ること」
人類が500万年の歴史を通して社会を作りあげてきたのは、自分たちを外敵や災害から守るためです。人間を守るために社会は作られたのです。社会そのものがセーフティネットであったはずです。
人類は恐竜や猛獣と闘い、病気や天変地異をかいくぐって生き延びてきました。そういう意味では、障がいがあろうがなかろうが、生きているだけでバンザイなのです。
だからセーフティネットは道具ではなくて社会の目的であるはずです。障がいがあろうが、歳を取ろうが、病気であろうが命を守るために悪戦苦闘するのが、社会の本源的な目的のはずです。ところが現状はどうでしょうか?
月2回の風呂介助サービスを増やすよう要求し、行政と交渉した時のことを思い出します。重度の障がい者や寝たきり高齢者は、床ずれや褥瘡(血行が悪くなり皮膚が壊死を起こす)が発生するので、毎日入浴しても追いつかないくらいです。交渉でH市福祉課長が「週1回に増やします」と回答したので、「こちらの要求は、毎日である」と告げたところ、「そんな贅沢言うたらあかんわ!」と言ったのです。頭に血が上りました。
「じゃあ、お前も入浴を週1回にしろ!」と叫んでしまいました。自分は毎日入浴しておきながら、目の前の障がい者に対してはそれが「贅沢だ」と言い放つ、その無神経さに怒りが湧いたのです。
課長の発言を撤回させ、交渉を続けましたが、結局、週2回で折れてしまいました。交渉の帰り道、週2回で諦めてしまった自分の不甲斐なさに情けなくなりました。私は風呂嫌いですが、それでも2日に1回は入ります。週2回では我慢できません。福祉や解放運動に関わる人間は、常に「自分ならどうなんだ」と問い直さなければならないと強く自戒しました。
その問い返しこそが福祉であり、セーフティネットの根本だと今も思っています。答えは、やっぱり自分たちの中にあるのです。自分たちの中から答えを創っていくべきです。
「愛と正義を否定する」
障がい者市民運動の沈滞が言われ始めていますが、社会運動全体がへこたれているのです。特に人と人との繋がりがとても希薄になっていることは、大きな問題です。「昔は良かった」と言いたくはありませんが、今の若い人たちは、自分の領域に他人が入ってくるのをとても嫌っているように見えます。しかし一方でスポーツ観戦やお笑い番組では、同じ様に盛り上がって、同じような反応を示すことで一体感を作ろうとしているように見えます。違っていて当たり前なのに、無理矢理周囲に合わせようとするのは、関係性が希薄な裏返しです。
こうした希薄な関係しかない社会を作り出してきた責任の一端は、私たち障がい者市民運動にもあります。
江戸幕府は300年、明治維新以降の大日本帝国はたかだか50年です。さらに戦後は60年余ですが、その中で障がい者の歴史も脈々として繋がっています。そういう歴史をしっかり見ないと未来は見えてこないと思います。
戦中を生きた高齢の障がい者は、「我々は人間じゃなかった」と当時を回想します。敗戦の数年前から日本は物資不足で配給制度になるのですが、障がい者は、戦えない「非国民」として配給の対象から外されていたのです。そうした人々が70年代に声を上げ行動を起こしました。
これに先だつ70年安保闘争の敗北は、社会運動全体の沈滞をもたらしました。もうダメだと思っていた70年、80年代にあって「愛と正義を否定する」といって登場したのが青い芝の会の運動です。これまで自分は「愛と正義」を信じて闘ってきたはずなのに、それを真っ向から否定され、「そんなもんは、健常者の勝手な愛だ」と言われたのですから、目が点になりました。
それは、誰にも理解できない、やけくそで、バラバラで、それでも人として命として異議申し立てをする障がい者市民運動でした。その中心人物=横塚晃一さんらの発する激烈なメッセージは、それまでの社会運動の根っこの部分をゆさぶり、出口を探していた当時の私たちにとって障がい者市民運動は、希望の星となりました。
こうした激烈な異議申し立てによって、現在の福祉制度は一歩一歩勝ち取られてきたのです。
その人たちが今の日本を見て、「こんなはずじゃなかった」と大きなため息をついています。いろいろな事柄が社会からの影響を受けすぎているのではないでしょうか。
未来を創るのは「夢」だ
闘いというものは、愛とか感動とかを生むものです。70年代の闘争は、混沌だったけれども愛や感動という不合理な感情で自分の人生を決めていけるチャンスがありました。そうしたものが今の運動にはどこにも見あたりません。
色んな理論や方針を考えることは必要です。でも未来を創るのは「夢」です。理論や方針はあくまでも道具にすぎません。
今の若い障がい者と人々は「何とか食べられる、それなりに安定した」生活を失うことを恐れているのではないでしょうか。安定した生活は大事ですが、あくまで手段のはずです。
私は、夢を食って生きていって欲しいと願っています。我々はどこから来てどこへ行くのか?どんな生を送るのか?を追い求めていくべきだし、それは過去脈々と受け継がれてきた障がい者市民運動に繋がることでもあると思います。
ヘルパー制度など自立生活を支える制度は行きつ戻りつしながら、徐々に整えられていますが、それらが全くない時代に自立生活を願いながら果たせず死んでいった障がい者が、私の周りにも数多くいます。彼(女)らの恨みこそがそうした制度を作りあげた原動力です。そうした恨みや悲しみを背中に背負って「何とかせんかい!」と自分に号令をかけたら、こんな人生になりました。
現代の障がい者市民運動も、彼(女)らの夢や挫折や怒りに思いを巡らせて、彼らに繋がろうとすることのなかに再生の大きな鍵があると思います。
命のつながりを糧にして
私の連れ合いは、乳ガンで6年間の闘病生活を送りました。最後はG病院で終末期医療を受けることになりました。「もう残りわずかの時間だから」と子どもたちにも会社を休ませて最後の時間を一緒に過ごすことにしましたが、最後は自宅でと思い、病院には無理を言って車イスに乗せて自宅に帰り着きました。
「家に帰ってきたで!」と告げると彼女は、「カツラと洋服を着せて」と私に頼みました。死期を悟り、準備を始めたのです。彼女の兄と子どもたちと私と4人が看取ったので、きっと幸せな最期だったと思いますが、最後の瞬間に4人の顔を見て彼女の眼から涙が溢れました。
あの涙は何だったのか? 未だに私は反芻しています。ただ、あの瞬間に確信できたのは、「人間は、障がいがあろうがなかろうが、繋がってなあかん」ということです。私は、領域として障がい者の問題に取り組んできましたが、問題の核心は、命の問題あるいは、人間の繋がりの問題だと思っています。
連れ合いを亡くして、かなりへこたれました。今も実はへこたれています。それでもそんなへこたれた自分を受け入れてくれたのは、やっぱり障がい者でした。それも人工呼吸器をつけた最重度の障がいを持つ青年が「河野さん、へこたれたらあかん。僕はへこたれてないからね」と言ってくれたのです。
今まで「世界を変える!」と言ってきましたが、残りの時間を彼(女)らと共に生きていける企業を作りたいと思っています。小さなことでもいいから、ちゃんと地べたにくっついて、彼らの存在が社会化できるような新しい事業を考えたいと思います。
現実は苦しいからこそ、楽しい事業。例えば障がい者が健常者を雇って運営するリサイクルショップなどかもわかりません。
「団結して闘おう」といいますが、逆のはずです。闘う中からこそ団結は生まれるのです。それを教えてくれたのが障がい者市民解放運動です。
これからも、誰にも理解できない、やけくそで、バラバラで、それでも人として命として異議申し立てをする障がい者市民運動を共に創っていきたいですね。(おわり)
(2009/05/15)