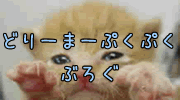特集:震災15年 -顔の見える関係が互いを守る
はじめに
「普段の生活の中で、顔の見える関係を作っておくことが、災害の時にも命を守る」。倒壊した文化住宅の下敷きになりながら、奇跡的に軽傷で救出された玉木幸則さんの教訓です。玉木さんは、自立生活支援センター、メインストリーム協会副会長。震災直後から仲間の生活再建・自立支援に奔走しました。
仮死状態で生まれた玉木さんは、脳性麻痺で話し方や歩き方に障がいがあります。小・中学校は普通校に通ったものの、高校は不本意ながら養護学校へ。独学で日本福祉大学に進学し、障がい者甲子園など多彩な活動を展開してきました。NHK番組「キラッと生きる」にも出演し、「主張する障がい者」として、政策提言も活発に行う玉木さんに、震災の経験から見えてきたことをお聞きしました。(文責・編集部)
アパートの下敷きに
編:まず地震の瞬間のことを話して下さい。
玉木: 気がつくと体の上に天井がのっていました。自宅は、家賃4万円というボロアパートの1階。訳がわからず必死でもがいても、起きあがれません。
そんな時、「どうしよう、家が潰れた」という2階の住人の声がすぐ上から聞こえて、2階が体の上に落ちてきたとわかりました。弱々しい声で「助けてくださ〜い。ここにいます」と叫んでいた私の声が、脳裏にこびりついています。ちなみに隣の部屋の学生は、即死でした。
妻は、ちょうど特別養護老人ホームの泊まり勤務でした。帰ってアパートを見た妻は、私は死んだと思ったそうです。
幸い2時間後に救助されました。アパートの大家さんが「埋まっているはずだ」と近所の人に声をかけてくれたそうです。近所に倒壊家屋がほとんどなかったため、地域の人々が総出で、ノコギリ・スコップを持ち寄って掘り出してくれました。
あらためて日頃のつき合いの大切さを痛感しました。というのは、大家さんとは、結婚する前から月に1度は家賃を支払いに行く時に世間話をしたり、畑で獲れた野菜を分けてもらったりという、つき合いがあったからです。地域に顔の見える関係があったことで、私は救われたのだと思います。
美しい「避難所の助け合い」?
家を失った私たち夫婦は、中学校の体育館に避難しました。でも震災当日は、弱肉強食の世界そのものでした。マスコミで報道された「避難所での助け合い」という美談は、避難所が、ある程度落ち着いてからのことです。人は、極限状況に追い込まれると自分のことしか考えられなくなるのでしょうか。
震災当日は、余震も続いていましたから、家が倒壊していない人も、みんな避難所に集まっていました。
私たちが避難所に着いたのは夕方でしたから、奥の方しか空いていません。トイレに行くのにも「すみません」と気をつかいながら、入り口に辿り着く状態で、トイレも我慢しなければなりませんでした。
私は、家が潰れ、食べるものもなく、パジャマに毛布1枚で寒さに凍えていました。しかし、家がある人たちは、布団や電気ポットなどを避難所に持ち込み、カップラーメンなどを食べていました。
そんな中で、夜中の11時頃、初めての救援物資=おにぎりが届いたのです。まず、子どもに配られましたが、後は早い者勝ちみたいになりました。
結局、元気で動きの速い人がおにぎりを掴み、障がい者やお年寄りが我慢する、といった状態となりました。私は、到底無理だろうとおにぎりは諦めて、この光景を妙に冷静に眺めていたことを覚えています。
悲しい思いをしましたが、これが日本社会の縮図のようなものだったのかもわかりません。
(2010/02/10)
WEBは抜粋版です。すべて読みたい方は購読案内をご覧ください。