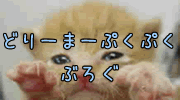特集:雑誌『そよ風のように〜』創刊31年
「転換期」だからこそ伝えたいことがある
100号記念インタビューは、小林敏昭さんです。りぼん社は、1979年の創刊以来、31年間で79号の雑誌と10数冊の著作を刊行し、障害者解放運動のメッセージを伝え続けています。
「まねき猫通信」も、今後を考える上で、先輩としてヒントをもらえると思います。編集者という立場で障害者運動に関わってこられた小林さんに、30年間を振り返ってもらいました。(編集部)
タブーを破る企画 誰でも読める雑誌
入部:まず、『そよ風のように街に出よう』発刊の目的と当時の運動状況をお聞かせ下さい。
小林: 創刊号は、入部さんの出産・子育てを取り上げました。脳性麻痺の女性が結婚し、新たな命を得たことを通して、障害者にとっての家族や自立の意味を問う特集です。重度障害者でベッド型車イスで生活する男性のヌード写真を掲載したこともあります。これらは、「障害者の性」というタブーを破る企画でした。
「青い芝の会」(脳性麻痺障害者の当事者組織)が、分裂していく中で、「障害者解放運動をもう一度立て直すために何ができるのだろう」と問い続け、雑誌創刊が決まりました。
しかし、障害者の多くは、義務教育からも排除されていました。このため、小難しい言葉がたくさん出てくるような理論誌では、障害当事者が参加しにくいし、たくさんの人にも読んでもらいたくて、誰でも読める雑誌として創刊されました。
入部: 創刊前に発起人の河野さんが、出版資金カンパを取りに来たことがありました。生活保護で生活していた私は「そんな金ない」と断ったのですが、しつこく説明を続けるのです。もの凄い熱意に根負けして、10万円出資しました。(笑)
小林:「自分たちのための雑誌を作ろう」と障害当事者にも呼びかけ、全国紙でも、「画期的な障害者雑誌創刊!」と大きく取り上げられました。当時の障害者問題の雑誌は、施設の職員や市民運動の活動家を対象にしたものくらいしかなく、「障害者自身の声を基にした、誰でも読める雑誌」として、全国から購読申し込みが殺到しました。
変革模索期に議論の場を提供
小林:80年前後というと、社会運動全体は停滞期でしたが、障害者運動は養護学校義務化反対運動(78年)が盛り上がり、国際障害者年(81年)へと繋がっていく変革模索期でした。
特に関西では、施設や家から出て自立生活を始める障害者がたくさん現れ、介護者が不足するくらいでした。当時は、介護保障などの福祉制度は未整備でしたので、介護者は全くの手弁当で「解放運動」への関わりを問われ、自らに問うことが求められました。しかし、そういう運動は中身が濃い反面、継続することが困難です。
介護者不足で地域生活を営めないという現実問題に突き当たり、新たな議論と実践が必要とされていた時期でした。
入部:「青い芝の会」も分裂します。当時、青い芝では、「介護者は、障害者の手足となるべきだ」との考え方が、大きな議論となりました。障害当事者の主体を尊重せよ!という趣旨ですが、健常者と障害者がお互いに変わり合ってこそ、解放へと向かうはずです。「介護者手足論」に反対した私は、除名処分を受けました。
小林:「『介護者手足論』は青い芝の思想的核心の一つだ」という人がいますが、それは間違いです。青い芝の創始者・横塚晃一さんらは、「障害者も健常者性をもっている。障害者自身も変わらなければ解放はない」と、相互変革論を強調しています。「介護者手足論」は、介護者不足で厳しい時期に、苦し紛れに出されたスローガンだと思います。
80年代に入ると公的介護保障要求者組合が結成され(88年)、アメリカで生まれたCIL(自立生活運動)を日本に定着させる運動も関東から広がります。
私たちは、公的介護保障の要求やアメリカ型運動とは少し距離を取りながらも、「青い芝の会」をはじめとする日本の障害者解放運動が培ってきた思いや実践をベースに、共に生きる社会をどう創っていくのか?との問題意識で、今もやっています。
(2010/11/29)
WEBは抜粋版です。すべて読みたい方は購読案内をご覧ください。