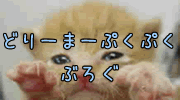当事者リレーエッセイ:初めて知った父の想い 村上博
肺ガンの末期と診断された父
昨年12月半ば末期の肺がんで入院した父は、長くて余命3カ月の宣告を受けた。父には知らせなかったが、姉兄弟4人は父の最後を覚悟した。
しかし、病魔は3カ月の猶予を与えなかった。入院して3週間余、今年1月7日未明、父は9年前に逝った最愛の母の許に旅立った。
6日前の1月1日、父は病院のベッドで歳の米寿を迎えた。妻が作ったバースデーケーキを前に、中学2年の三男と3人で、最後となったハッピーバースデーを歌った。5歳まで米国シアトル市で育った父は、パーコレーターで淹れたコーヒーが大好きだった。入院以来、流動食も食べなかった父が、持って行ったコーヒーをごくごくと嬉しそうに飲んだ。
病床における父との対話
これが最後のチャンスと考え、毎日病院に通い、父と話した。肺の機能が十分でないため息苦しく、体力を消耗させてしまったが、父は実によく答えてくれた。
高校入学の折、高校の校長は「校舎の改造要求をしないこと、生徒が故意に階段から突き落としても責任を求めないこと」を条件に、私の入学を認めた。同席していた両親も何も発言せず、私が「それでいいです」と返事をした。 〝15の春の出来事〟 が、長い間、私を苦しめた。
私は1歳半の時、小児まひで大学病院に入院した。母は5歳と3歳の姉兄の面倒を祖母に頼み、3カ月間泊まり込みで看病したことは子どもの頃聞かされて知っていたが、当時の父はどんな気持ちだったのかを尋ねた。
父の熱い想いに触れた瞬間
「死ぬとは思わなかったが、最悪の気分だった」 と、父の感情を初めて聞いた。それでは、入院中の3カ月は、授業中も気が気ではなかった?と尋ねると、なんと授業が終わると毎日自転車で大学病院に通った、と答えた。母と共に病院に泊まり込み、朝から学校へ通勤したそうだ。当時、郡部の学校から熊本市内までは舗装されていないガタガタの悪路で、片道2時間近くを要した。
私は38歳の時、2カ月のアメリカ滞在をきっかけに、障害を受容できた。私の人生はその後劇的に転回し、15の春の出来事さえも気持ちの中では貴重な体験となっていた。しかし長い年月、障害を持った私の存在を父に認められてきたのかどうか確信出来ていなかった。だから、父が病院に通い続けた3カ月の出来事は、衝撃に近かった。その事実を父から直接聞いたことは、私の疑心暗鬼を完全に払拭し、父の熱い想いに触れた瞬間だった。
61歳にして初めて知ったこの事実は、死期を目前にした父から私への、最大のエールでありプレゼントとなった。
WEBは抜粋版です。すべて読みたい方は購読案内をご覧ください。