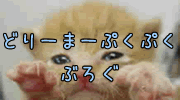当事者リレーエッセイ:初めて知った父の想い 村上博
看病の日々
89歳だった母が他界した。入院して47日目だった。毎日、朝7時には病院に行き、9時に職場へ。夕方5時過ぎには再び病院へ消灯まで付き添った。病院から「治療に抵抗して点滴チューブを抜き取るので家族の付き添いを」と要請されていたし、これまで親孝行らしいことは何もしてこなかったこともあって、とにかく展望なき病院通いを自らの責務と課したところだった。
食事の介助をしても不服を言う母にイライラしたり、無理やりベットから降りるのを押しとどめたりと、親孝行とはいえない様相であったし、正直日に日に疲れがたまっていくのを感じていた。しかし早朝の病院の駐車場で守衛さんと挨拶を交わし、同室の患者さんと言葉を交わすのが気の休まる日課でもあった。
悲しいことに、入院期間中に同室のおふたりの方が他界された。「イチゴを内緒で食べたい」と言い残したAさん、「腰が痛くてこんなもの役に立たん」と体位変換ポンプに不満たらたらだったBさん、そして最後まで医療を信じることなく「病院に居たくない」と主張し続けたわが母、それぞれの人生を感じとれるこれまでにない時間を過ごした。
反骨精神とやさしさ
母は戦争の最中に京都から滋賀の田舎に養女として移り住んだ。やがて助産院を開業して、何千人という赤ん坊を取り上げ、一方なれない米づくりをして、京都と滋賀の二人の祖母の女所帯を養ってきたのだった。反骨の精神を持ち、「なにくそ」の気持ちが大切だというのが口癖であった。その昔、我が家の田植えはにぎやかだった。何人もの人たちが「お産の時に世話になった」と手伝いに来るのが恒例になっていたからだ。父親が飼っていた鶏をつぶしてすき焼きをするのがこれも恒例になっていて貧しさの中にもあったかな空気が流れていた。母は貧しい人からお金はもらわなかったり、産後ゆっくり休めない妊婦さんを自宅に泊めたりしていた。驚いたことに産婆である母のところに怪我人が運ばれてきて応急処置をしていることがたびたびあった。無医村であった時代だ。ちなみに私はそのころ「産婆さんのボンやん」と呼ばれていた。 母親のいない時間がどんどん過ぎていく。人生として最後まで反骨、抵抗を続ける闘士でありたいと思っている。
WEBは抜粋版です。すべて読みたい方は購読案内をご覧ください。