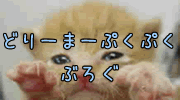当事者リレーエッセイ:『TOKYO2020』 村上博
56年ぶりの熱狂
9月7日、アルゼンチンのブエノスアイレスで開かれたIOC総会で2020年オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決まった。最大のライバル 〝スペイン・マドリード〟は、最初に脱落。アジアとヨーロッパの架け橋を合言葉にした 〝トルコ・イスタンブール〟と東京との決選投票の結果、ロゲIOC会長が「TOKYO2020」と発表の瞬間、日本中が狂喜乱舞した。決定の要因は、2都市を圧倒した最終プレゼンテーションの内容だった。
日の丸に涙する五輪
「生きているうちには二度とない」と洗脳され、世紀の大イベントなんだ!と、あっという間に五輪少年が誕生した1964年の東京大会。
その時、中学2年、14歳の私は、東洋の魔女たちの試合をテレビの前で「日本、チャチャチャ!」と必死に声援した。盆や正月どころか、入園して退園するまで帰省が許されなかった退屈な肢体不自由児施設での生活も2年半を経過していた。
64年東京オリンピックは、開業したばかりの東海道新幹線に象徴される高度経済成長と時期を同じくしていた。選手強化の成果は女子バレーボールのほか、体操、重量挙げ、柔道、レスリングなどの種目で金メダルを含め、史上最高数のメダルを獲得し、日本中が熱狂した。テレビも新聞各紙も連日大きく報道、オリンピックの興奮は日本中を覆い、私もその渦にどっぷり浸った。メインポールに翻る日の丸を見て、軍国少年ならぬ、五輪少年は無条件に感動し喜んだ。それは退屈な施設暮らしの反動だったのだろう。
熱狂の陰で
しかし、国民的熱狂は肝心なものが見えなくなってしまう。国を挙げて戦争へ突き進んだ過去の歴史を引き合いに出さずとも、為政者にとって都合が悪いことから目をそらさせることができる。64年東京オリンピック以降、高度経済成長に付きものの社会的格差が広がるなか、障がい者は社会的弱者の代表的な存在となったため、地域での自立生活運動が起こったのは必然だった。
今こそ、想いを巡らそう!
アスリートの感動的なプレゼンテーションは良いとしても、「汚染水は0・3平方キロの港湾の中に完全にブロックし、コントロールしている」「東京には影響はない」と言い切った安倍総理の発言は許せない。東京招致の熱狂を利用し、福島の切り捨てを世界に向かって宣言したに等しい。収束どころか、世界への原発売り込みを成長戦略の柱に据え、先が見えない福島原発事故の深刻さから国民の目をそらそうとしている。
今こそ、故郷を追われ、遠隔地で不自由な生活を強いられている障がい者仲間たちに想いを巡らし、福島に、原発事故に目を向けようと思う。
WEBは抜粋版です。すべて読みたい方は購読案内をご覧ください。